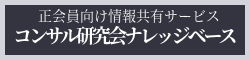契約書をみるポイント2(解除条項)
理事
弁護士 亀井洋一
1月に続いて、契約書のレビューに当たって気付いた点をレポートします。
前回も少し触れましたが、契約書には、相手方に一定の信用不安事由が発生した場合に契約を解除できる旨の条項が設けられています。この条項がないと、相互に債権債務を負担する双務契約の場合、相手方から履行を受けられるかどうか怪しいにもかかわらず、先履行義務が発生してしまうことがあります。
例えば、継続的な売買契約では売主が対象物を給付して、その後に代金を支払ってもらうのが普通であり(「月末締め翌月末払い」などとされます)、そのままでは買主に信用不安事由が発生しても売主が履行しないと債務不履行責任を負うことから、契約の拘束から逃れることができるようにしておく必要があります。
もっとも、そのような事態が頻繁に起きる訳ではなく(起きたら困りますよね)、滅多に適用されない条項ですので、旧い規定がそのまま残っていることがあります。
さすがに、今では「和議」とか「破産宣告」などの文言を見ることはほとんどなくなりましたが、「会社整理」は結構ありますし、典型例の破産についても「破産手続開始の申立てを受け、または自ら申し立てたとき」という正確な記載がされている場合は必ずしも多くありません。
また、当事者の一方が「振り出した、または裏書きした手形が不渡りとなったとき」とか、「合併したとき」当然に解除できるという条項もよく見かけますが、裏書きした手形の不渡りは振出人(約束手形の場合)の信用不安事由であっても直ちに裏書人の信用が損なわれる訳ではありませんし、子会社を合併しても信用を害することにはならないでしょう。
正確に記載すると「自ら振り出した、または引き受けた手形」とすべきですし、合併については、私は「合併により消滅会社となったとき」と記載したり、「(但し、本契約の履行に影響する場合に限る)」などの記載を追加したりしています。
なお、裏書きした手形が不渡りになったときでも、そのために裏書人が多額の遡求債務を負ったり、連鎖倒産に巻き込まれるなど、信用を害することもない訳ではありません。
そのため、解除の項目には、必ず「その他、前各号に相当する本契約を継続しがたい事由が生じたとき」という「バスケット条項」を入れるようにしています。
合わせて、被解除者が解除者に対して債務を負担しているときは期限の利益を喪失するという「期限の利益喪失条項」と(解除者が債権を有しているときは、直ちに請求できるようにするためです)、解除により解除者に損害が発生したときは、被解除者はその損害を賠償するという賠償責任を規定しておきます(「解除によって発生した損害」は必ずしも「債務不履行による損害」とは限らないからです)。
もちろん、このような条項が効力を発揮することなどない方がよいことは言うまでもありません。