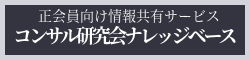契約書をみるポイント1(対等性の観点から)
理事
弁護士 亀井洋一
企業法務を扱っていると契約書のレビューを依頼されることがよくあります。
契約書は見慣れているという方も多いかも知れませんが、これから、私が体験した契約書について、何回かに分けて、気楽にお読みいただけるように余り法律的ではない観点から採り上げてみたいと思います。
まず、初回ですが、時おり一方的に一方当事者に有利な契約書を見ることがあります。
例えば、支払停止や破産手続開始など信用不安事由が発生した場合の解除条項について、一方のみが解除権を有していたり(「乙に以下の事由の一でも生じた場合には、甲は何ら催告することなく本契約を解除できる」など、解除できるには「甲」だけ!)、一方のみに反社会的勢力に属さないことを表明保証させるというような契約書があります。
このような契約書は、自分を守るという観点からは十分な合理性があるのですが、公正さを疑われてもやむを得ない点で感心できません(相手方が異議を述べなければよいというものでもないでしょう)。
私が相手方の立場でレビューする場合は、もちろん双方が対等になるように修正しますが、このような契約書を提示してくる相手方に対しては強い警戒心を抱きますので、どうでもよいような細部についても徹底的にチェックします。
一方、形式的に対等でありながら、実質的には一方に有利な契約があります。
例えば、売買契約を例にとると、遅延損害金の約定が設けられていることが、よくあります。
この場合、当事者双方に適用があるとすると一見して対等なように見えますが、売買契約で債務を負うのは通常は買主なので、実は主に売主の権利保護に資する規定なのです(債務不履行による損害賠償など売主が債務を負担することもありますが)。
また、守秘義務条項もほとんどの契約書に規定されていますが、主に一方の当事者が情報を開示する場合は、この義務を負うのも主に相手方になります。
このような契約では、義務を負わせる側はできるだけ厳しく相手方を拘束したいですし、義務を負う側は、逆に負担を軽くしたいでしょう。したがって、どちら側で作成するかにより、契約書に盛り込む文言も変わってきます。
弁護士が契約書をレビューするときは、このように依頼者がどちら側なのかを意識して「さじ加減」しているのです。